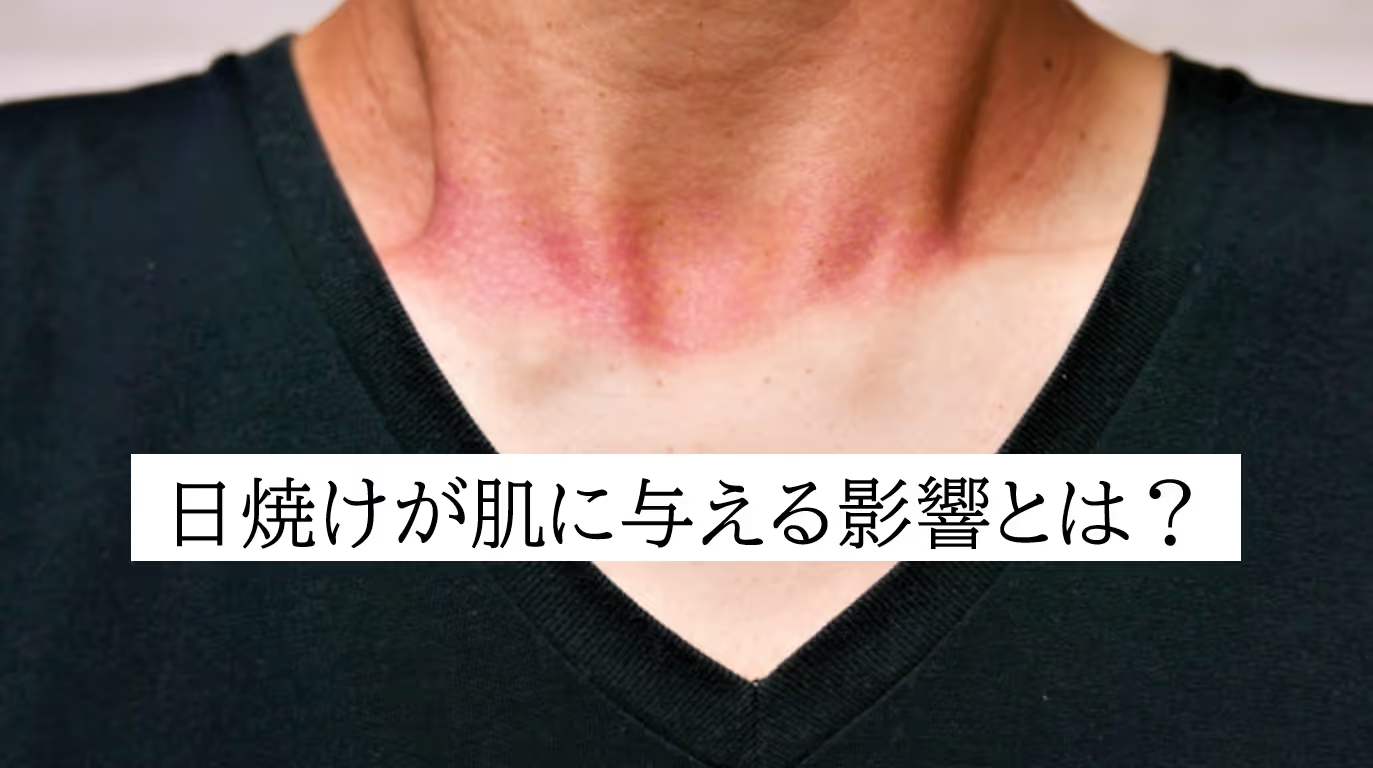勉強を頑張るあなた。
試験で結果を出したい、資格を取得したい、単位を取りたい、教養を身に付けたい。
勉強を頑張りたい理由はさまざまでしょうが、勉強に力を入れれば入れるほど、他のことに時間を使えなくなりますよね。
そうなるとだんだん運動不足になっていきます。でも勉強で結果を出すためには仕方ない。そう思っていませんか。
結論から言うと、運動をすることで脳の機能が向上して、勉強でより良い結果を出すことにつながるのです。
「スマホ脳」でお馴染みのアンデシュハンセン氏の著書「運動脳」を参考に、運動が脳にもたらす好影響についてお伝えします。
文武両道が最強の理由
みなさんの学生時代、運動もできて、勉強もできるいわゆる万能タイプの生徒っていましたよね。そんな人を見て、あの人は天才だから私たちのような凡人は寝る間も惜しんで勉強しなきゃと思った人も多いのではないでしょうか。
しかし、文武両道だったあの人は、実は才能があるから文武両道だったのではなく、運動の効果によって高い学習効果を得ていた可能性もあるのです。
運動で記憶力が向上する

ある研究によると、一年間有酸素運動をおこなったグループと何もしなかったグループを比較すると、有酸素運動をしたグループは2%も脳の海馬が成長していたそうです。海馬とは、脳の記憶を司る部分でここが成長するということは記憶力の向上が期待できます。
英検やTOEICなど、英単語をたくさん覚える必要がある人なんかは記憶力の向上は得点アップに必須ですよね。
軽い有酸素運動を続けるだけで、記憶力が向上するとしたらやらない手はないですよね。
ただし、過度に運動をすると逆効果になるという結果も出ているので、適度な運動をすることを心がけるといいでしょう。
運動で集中力が向上する

勉強にもっとも必要な要素。それは集中力だと私は考えます。
さあ、勉強しようと思ってもすぐに集中力が途切れてします。スマホを見てしまったり、漫画を読んでしまったりと現代はあらゆる手で私たちの集中力を阻害しようとするもので溢れかえっています。
実は集中力も運動によって向上させることができるのです。
集中力には、「ドーパミン」という脳内物質が大きく関係します。
ドーパミンが分泌されると心地よい気分になります。ある行動をしてドーパミンが分泌されると人はもっとその行動をしようとします。逆にドーパミンが分泌されないとその行動に興味を失ってしまうのです。これが、物事に集中したり、集中力が切れるということです。
つまり、勉強中にたくさんドーパミンが分泌されれば、集中力はどんどん高まっていくということです。
ドーパミンの分泌を高める行動、それが運動です。負荷の強い運動をすればするほど、脳内ではドーパミンが分泌されます。これがあなたの集中力を向上させてくれます。
集中力不足で悩んでいるあなた。さっそく運動をしましょう。
どんな運動をするべきか
運動が記憶力や集中力の向上に大きな影響を与えるとしたら、運動しない手はありませんよね。
では、具体的にどのような運動をするべきなのでしょうか。
心地よいと感じる負荷の有酸素運動

記憶力や集中力を高めるために有効な方法は有酸素運動です。ウォーキングやランニング、水泳など、呼吸をしながら行う運動のことです。筋トレや短距離走は有酸素運動ではありませんので注意が必要ですね。
有酸素運動をする際には心地よいと感じるくらいの負荷で行うことが重要です。疲労困憊してしまうほどの負荷で運動をすると逆効果になるという研究結果が出ています。記憶力を高めたいからといって無闇激しい運動は避けましょう。
高負荷の有酸素運動をしたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
運動をすると勉強にもとても役に立つことがおわかりいただけたでしょうか。
ぜひ、勉強のために運動の時間を削っていた人は運動を取り入れてみてください。
気がつくと、あなたの脳の機能が向上していることを実感できるはずです。
それでは、良き勉強ライフを!
「運動脳」では、勉強のほかにも運動が人体にもたらす好影響についてたくさん紹介していますので、ぜひ読んでみてください。
アンデシュハンセン氏の代表作「スマホ脳」も非常に有益ですので、一度読んでみましょう。


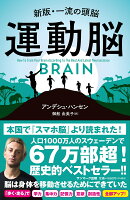
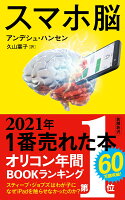








.avif)